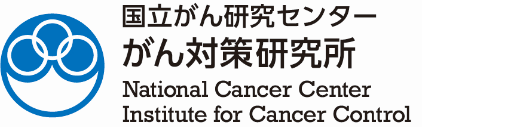トップページ > 用語解説
用語解説
ガイドラインにおける用語について解説する。用語の解説は平成10年3月に公表された厚生省老人保健推進費等補助金老人保健福祉に関する調査研究事業「がん検診の有効性評価班」報告書(主任研究者 久道茂)に基づき、追加・修正を行ったものである。
あ行
アナリティック・フレームワーク(analytic framework)
対象集団の選定、スクリーニングの実施、偶発症の発生、診断、治療、予後、に至るまで、様々な関連する解析のための枠組みを図式化したもの。個々の事象に関しての検討課題(key question)を列挙し、それに沿って研究データを収集し、評価する検診に関す全体の研究データを集約する手法。US Preventive Service Task Forceでも、第3版から採用され、検診が有効であると評価されるために必要な根拠の論理的な流れや繋がりを図示する。
インテンション・トゥ・トリート分析(intention to treat analysis)
検診の有効性を評価する無作為化比較対照試験において、割り付けられた検診プログラムをすべての対象者が適切に受けるとは限らない。対照群に割り付けられた対象者が、何らかの理由により、研究群の検診プログラムを受診する可能性もある。インテンション・トゥ・トリート分析とは、対象者が当初割り当てられた検診プログラム(あるいは検診を受けないというプログラム)を実際に受診したか否かにかかわらず、割り付けられた群に従って分析することをいう。対象者が方針に従わなかったことも含めて、検診の有効性を評価する第一義的な解析手法である。割り付けられた群からの脱落者を除外した分析をper protocol analysis、on treatment analysisという。
エビデンス・テーブル(evidence table)
収集した文献を、一定の評価基準に沿って、その要約を記載し、データベース化したもの。アブストラクト・テーブルとも呼ばれる。エンドポイント(endopoint)
有効性評価の評価指標となる病変あるいは身体状態。オッズ比(odds ratio:OR)
一般に症例対照研究やロジスティック回帰において、要因曝露と疾病との関連の強さを評価する指標。検診の効果を評価する場合は「検診受診」を要因曝露とみなし、「当該疾病による死亡」を症例とみなす。オッズ比(OR)が1.0以下の場合、要因曝露(検診受診)が疾病(当該がんによる死亡)を予防したことを意味し、1.0以上では死亡リスクが増加したことを示す。死亡率が小さい場合の相対危険度の近似値であり、相対危険度と同様の解釈が可能である。すなわちオッズ比(OR)0.3の場合、検診を受診することで本来1の死亡率が0.3に減少した(70%の死亡率減少効果を示した)と表現される。
か行
過剰診断(overdiagnosis)
がん検診はがんによる死亡を防ぐことを目的に、がんによる症状が発現する前に発見し、治療するために行われる。ここには、がんは放置すると進行し致死的となるという前提が存在するが、放置しても、致死的とはならないがんも、一定割合で存在する。端的な例はがんが進行して症状が発現する前に、他の原因で死亡してしまうようながんを早期に発見する場合である。こうした例は、がんの成長速度が極めてゆるやかであったり、極めて早期にがんを発見した場合、あるいは、がんが発見された人が高齢者であったり重篤な合併症を有する場合に生じやすい。このようながんを診断し、治療することは、受診者にとっての不利益につながることから、過剰診断と呼ばれる。がん検診の有効性(effectiveness of cancer screening )
がん検診の有効性は、がん検診の対象となるがんの死亡率が減少することを指標として評価する。それ以外の指標(発見率、切除率、生存率など)を用いて、がん検診の評価を行う場合にも、わが国の一部では「がん検診の有用性」という表現が用いられることがある。しかし「有用性(usefulness)」という表現は一般的ではなく、諸外国では「有効性(effectiveness/efficacy)」をもって検診の評価われることから、当ガイドラインでは、「有効性」と「有用性」の言葉を区別し、有効性に関する検討を行った。感度の測定法(同時法・追跡法)(diagnostic method / follow-up method)
感度を測定する際に、同一被検者に複数の検査法(感度を求める検査と確定診断に用いる検査)をほぼ同時に行い、確定診断に用いる検査を至適基準(gold standard)として、感度を求める方法を同時法と呼ぶ。一方一つの検査法を行なった後、がん登録などで把握されたその後の罹患を至適基準(gold standard)として、感度を求める方法を追跡法と呼ぶ。検診で発見されない中間期がんを把握できるのは、後者の場合だけである。検査後何年までの罹患を把握するかによって、値は異なってくる。また、同時法・追跡法とも至適基準(gold standard)と定義するものの精度により、結果の信頼性が影響を受けるため、異なる方法で求められた感度を単純に比較することはできない。QALY 質調整生存年(Quality Adjusted Life years)
経済評価を行う際に、評価するプログラムの結果の指標として用いられる。単純に生存期間の延長を論じるのではなく、生活の質(QOL)を表す効用値で重み付けしたものである。QALYを評価指標とすれば、生存期間(量的利益)と生活の質(質的利益)の両方を同時に評価できる。効用値(utility)は完全な健康を1、死亡を0とした上で種々の健康状態をその間の値として計測される。たとえばAという治療をうけた場合、5年間生存期間が延長すると仮定し、その後の効用値0.8とすると、QALYは5(年)×0.8=4(QALY)となる。系統的総括(systematic review)
当該分野のオーソリティが文献をまとめて解説をつける総括(review)では、著者の主観が入り込むことにより、偏った文献の選択や解釈が生じる可能性がある。このため客観的な真理を追究する立場から、答えるべき疑問を特定し、一定のルールの下に文献を検索し、批判的吟味を加えてまとめあげられたものを系統的総括と呼ぶ。英国のCochran Libraryは、これを継続的に実施している代表例である。検査の精度(accuracy)
検査の目的は、病気のある者とない者とを識別することにある。病気のある者を「陽性」、病気のない者を「陰性」と正しく判定する能力が検査の精度である。具体的には感度、特異度などの指標がある。これらはトレード・オフの関係(トレード・オフの項 参照)にあり、個々に議論するべきではなく、併せて議論しなければならない。
- 感度(sensitivity)
がん検診の場合にはある検査が、がんのある者を「陽性」と正しく判定する割合。下表の中、a/(a+b)の値である。感度が高いことは、検査法の見落としが少ないことを意味する。
- 特異度(specificity)
ある検査が、がんのない者を「陰性」と正しく判定する場合。下表の中、d/(c+d)の値である。特異度が高いことは、偽陽性が少ないことを意味し、有病率が低い疾患であるがんを対象とした検診の場合では、最も重要な指標である。
- 偽陰性(false negative:FN)
がんがあるにもかかわらず、検査で「陰性」と判定されるもの。下記の表のbに該当する。見逃し例(interval case)ともいう。偽陰性率は、(1-感度)として計算される。
- 偽陽性(false positive:FP)
がんがないにもかかわらず、検査で「陽性」と判定されるもの。下記の表のxに該当する。偽陽性率は、(1-特異度)として計算される。
- 陽性反応適中度(positive predictive value:PPV)
検査で陽性と判定された者における患者の割合である。下表の中、a/(a+c)の値である。感度と特異性は検査法固有の性能によって決まるのに対して、陽性反応適中度は集団における有病率によっても影響を受けるので、評価指標として用いる場合に留意する必要がある。
| 検査 | |||
| 陽性 | 陰性 | ||
| がん | ある | a | b |
| なし | c | d | |
検診(screening)
無症状の者に検査を実施してがんを早期に発見し、早期治療を図ることでその疾患の予後を改善させる(当該がん死亡率を減少させる)こと。スクリーニング検査から精密検査、そしてがんの発見と治療への橋渡しに至る一連の過程およびシステムをいう。
効果(effectiveness)
現実の一般的な集団における有効性の指標。保健医療技術を実際の場に普及させるに当たっては、理想通りにはいかない場合も多くなる。例えば、がん検診の受診を勧められても受診しない者もいれば、検査技術も均一化し難い状況も発生してくる。このような一般的な状況下での有効性を検討するものである。したがって、理想的な条件下での効能は十分あっても効果に乏しいという現象も起こり得る。効能(efficacy)
理想的な条件下で理想的な方法により検診などの保健医療技術が実施された場合の有効性の指標。例えば、検診の受診を推奨された対象者すべてが検診を受診し、その検査技術も完璧なレベルで行われている状況下での有効性を検討するものである。
効率(efficiency)
単位時間または単位費用当たりで得られる効果の指標。得られた効果を、それに要した時間量または費用で割ることによって計算される。
構造化要約(structured abstract)
目的・デザイン・方法・結果・結論などの論文の項目と同様の構造で、内容が簡潔にまとめられた抄録。短時間で読むことができ、同様の文献との比較が容易である。コホート研究(cohort study)
ある特性(生活習慣や検診の受診歴など)をもった集団(これを「コホート」という)に対して疾患の罹患や死亡などを追跡することによって、その特性と疾患のリスクとの関連を明らかにする研究。例えば、自発的にがん検診を受診した群と受診しなかった群とで、その後の当該がん死亡率を比較する。無作為化比較対照試験の各群をコホートと表現することもあるが、一般的にがん検診のコホート研究は、受診率の高い集団と低い集団との比較、あるいは、単一コホートの中で受診群と未受診群の死亡率を比較評価するものを指す。コンタミネーション(contamination)
汚染、混入などと訳す。がん検診の有効性評価の場合には、無作為化比較対照試験において対照群(検診を受診しないはずの群)に割り付けられた者のうち、実際は検診を受診する者の割合として用いられる。がん検診に関する無作為化比較対照試験の理想は、検診群に割り付けられた者全員が受診し(100%のコンプライアンス)、対照群に割り付けられた者のうちだれも受診しない(0%のコンタミネーション)という状況下での両群の当該がん死亡率の比較である。しかし、各個人の行動を強制することは現実には不可能なので、この2つの問題が起こってくることはやむを得ない。コンタミネーションが高い場合、実際は検診に効果があったとしても、見かけ上の効果(検診群と対照群の死亡率の差)は低く測定される。コンプライアンス(compliance)
受容度、応諾率、遵守程度と訳す。対象者のうち、保健行動、医療上の指示を受容する者の割合。例えば、無作為化比較対照試験において検診群に割り付けられた者のうち、実際に検診を受診する者の割合を意味する。コンプライアンスが低い場合、実際は検診に効果があったとしても、見かけ上は十分な効果(検診群と対照群の死亡率の差)が観察されない可能性がある。さ行
時系列研究(time series study)
ある集団におけるがん死亡率などの動向について時間の経過をおって観察し、その間に変化する様々な要因との関係を検討する研究手法。例えば、がん検診や新しい治療技術の導入の前後で死亡率が著明に減少していれば、これらの効果を示唆するものといえるが、単純にがん検診のみの効果とはいえない。子宮頸がん検診の有効性は主にこの方法により検討されてきた。しかし、同時期に変化した要因が交絡している可能性もあり、がん検診の有効性については慎重に考慮されなければならない。
至適基準(gold standard)
新しい検査法を評価するときに、比較の基準になる方法や手段を指す。たとえば検査法の感度を評価するときに、至適基準として、同時に行った別の検査法(たとえば便潜血検査を評価する場合の全大腸内視鏡検査)とする場合や、がん登録で罹患を把握する場合、あるいは生検組織や剖検診断とする場合がある。至適基準自体の正確性が異なるので、単純に感度だけを比較するのではなく、至適基準をどう定義したのかに着目する必要がある。
死亡リスク(mortality risk)
死亡の危険性を数量的に表すもの。ある要因を持つ者の集団と持たない者の集団(例:検診の受診者と非受診者)との間で、死亡の危険性を比較する場合、死亡に関する相対危険度やオッズ比によって死亡リスクを検討する。死亡率(mortality rate)
ある集団内で観察された死亡数を、その集団の観察人年(対象集団1人1人の観察期間の総計)で割ったもの。通常は1年を単位として人口千対、人口10万対等で表す。総死因あるいは各死因別に計算できる。受診率(screening rate)
対象集団のうち検診を受診した者の割合。特に、老人保健法による検診の対象者とは、運用上、「それ以外の社会資源や制度をもってしても受ける機会のない住民を対象とするもの」とされている。すなわち、他の医療保険のサ―ビスによる健康診断を受けられる者や医療機関で管理されている者を除外した結果が、ここにおける対象集団に該当する。この定義や計算法は市町村によって異なる。証拠のレベル(level of evidence)
個々の検診について、一定のルールに従って、当該検診の有効性に関する証拠の確実性をコード化したもの。本ガイドラインでは1-4に分類し、数字が小さくなるほど(バイアスが含まれる度合いが少なく、妥当性の高い知見となる)証拠の信頼性が高いとした。また1と2については、++、+、-のサブコードをもうけ、同じ1であっても++がもっとも信頼性が高く、-がもっとも信頼性が低いものと定義した。
症例対照研究(case-control study:CCS)
過去にさかのぼって後向きに調査する代表的な疫学研究手法で、ある要因の有無による当該疾患罹患あるいは死亡のリスクの違いを検討するもの。がん検診の評価の場合には、当該がんで死亡した症例群(あるいは進行がんに罹患した症例)と症例群死亡時に生存している健常者に対照群をある集団より選別し、両群に対して、がん検診の受診歴(や過去の生活習慣、環境曝露)に関するデータを収集して、がん検診受診による当該がんによる死亡リスクの低下を検討する。信頼区間(confidential interval
特定の水準(たとえば95%)の信頼度の中で、真の値を含んでいると考えられる測定値の範囲。この範囲が狭い場合、計算の結果得られた値の信頼性は高いと考えられる。また、Aというデータの95%信頼区間がBという値を含んでいない場合、推定値Aは値Bと統計学的に有意差(p<0.05)があるいえる。死亡率減少効果を示す相対危険度やオッズ比の場合、95%信頼区間の上限が1を下回れば、統計学的有意に死亡率減少効果を示したことになる。
推奨(recommendation)
ガイドライン作成委員会が、科学的根拠に基づいて判断した、がん検診実施の有無についての勧め。本研究班においては、個々のがん検診について対策型検診・任意型検診の実施の有無を「推奨グレード」として示している。
スクリーニング検査(screening test)
無症状の者を対象に、疾患の疑いのある者を発見することを目的に行う検査。例えば、胃がん検診の胃部間接X線撮影、大腸がん検診の便潜血検査などが、これにあたる。
生存率(survival rate)
ある病気をもつ患者集団において、ある期間までに生存している者の割合。がんでは、一般に5年生存率が治癒率の代わりに用いられることが多い。一定期間まで生死が確認できなかった例(消息不明例や観察打ち切り(観察期間が短いものや、転出など))を打ち切り(censored case)とよび、これらが多い場合は、信頼性に欠ける。がんの臨床研究では、Kaplan- Meier法を用いた実測生存率(全死因死亡による生存率:observed survival rate)や、補正生存率(当該がん死亡による生存率:cause-specific survival rate)が用いられることが多い。精密検査(work-up examination)
スクリーニング検査で陽性と判定された者を対象に、その疾患の診断を目的に行う検査。例えば、胃や大腸の内視鏡検査や生検(バイオプシー)による組織診などがある。一般にはスクリーニング検査とは異なる検査法であり、スクリーニング検査の単純な再検査(たとえば便潜血陽性の場合の、便潜血の再検査や、喀痰細胞診D以上に対する喀痰の再検査)とは区別しなければならない。説明と同意、インフォームド・コンセント(informed consent:IC)
病状や検査・治療方針について、医師等が患者や受診者に対して複数の選択肢があることやその行為による利益と不利益を事前に十分に説明し、患者や受診者自身が理解し納得した上で医療行為を受けてもらうこと。現代の臨床医学では倫理面から不可欠であり、すべての医療行為において、必須とされている。セルフセレクション・バイアス(self-selection bias)
検診受診者と非受診者との間で、がんの罹患、死亡及び予後に関するリスク要因の分布が異なることによるバイアスである。発見動機別のがん患者の生存率の比較の際には、一般に、検診受診者は健康意識が高く、喫煙率が低いなどにより、もともと生存率が高いのかもしれないので、検診発見例の生存率が症状発見例よりも高かったとしても、検診の効果とはいいきれない。また、検診受診者における死亡率減少を検討するための症例対照研究の際には、検診受診者は健康意識が高いために、発病リスク自体が低くなる可能性がある(healthy screenee bias)。逆に、受診者で当該がんの家族歴を有する者が多く含まれるという逆のバイアスが生じる可能性もある。したがって、症例対照研究などの観察的研究において検診受診者と非受診者との間で当該がん死亡率に差があっても、このバイアスのために、それが真に検診効果のみによるものか判別し難いことがある。相対危険度(relative risk:RR)
コホート研究や無作為化比較対照試験において、要因曝露と疾病との関連の強さを評価する指標。ある要因の曝露を受けていない群に対する曝露を受けている群の罹患率(または死亡率)の比として求められる。例えば、あるがん検診を受けた群における当該がんの死亡率が人口10万対30で、その検診を受けていない群での死亡率が同50であった場合、30/50=0.6が相対危険度(RR=0.6)となる。この場合、検診受診者では、非受診者よりも当該がんの死亡リスクが60%になる(40%の死亡率減少効果)と解釈され、検診による死亡率減少効果が定量的に示される。
組織型検診(organized screening)
対象者を中央登録システムで管理し、事前に定められたガイドラインに従って、組織的に管理して行われる検診。集団を対象としたがん検診として、集団の死亡率減少を目的として実施するものを示し、公共的な予防対策として行われる。対象者や検診間隔、精検方法や治療法が明確に定義されており、受診率、発見率、偽陽性率、偽陰性率などがモニタリングされ、プログラム全体が、適切に運用されているか管理されているものを指す。北欧や英国では、国民のがん死亡減少を目的とした政策として、乳がん検診や子宮頚がん検診のOrganized Screeningが行われている。一方、わが国の老人保健事業によるがん検診は、組織型検診としては不十分な現状にある。た行
対策型検診(population based screening)
対象集団全体の死亡率の減少を目的とし、公共的な予防対策として行われる。対象は、地域住民など、特定の集団が対象となる。無症状であることが原則であり、有症状者や診療の対象となる者は含まれない。対策型検診は、死亡率減少効果が科学的に証明されていること、不利益を可能な限り最小化することが原則となる。老人保健事業による市区町村のがん検診や、職域における法定健診に付加して行われるがん検診が該当する。滞在時間(sojourn time)
検診で発見可能になる時点から、症状出現までの時間。がんの種類によっても異なるが、スクリーニングに用いる方法によっても異なる。新しい方法によって発見されるがんが、従来の方法で発見されるがんに比べて小型化あるいは早期がんの占める率が高くなる場合は、新しい方法による滞在時間が従来の方法よりも延長していることを意味する。滞在時間の延長は、集団全体で見ると、特定の時点での発見可能例の割合(=有病率)の増加を来たすので、発見率が高くなる。滞在時間があまり長期間に延長すると、症状の出現する前に、他の疾患で死亡する例(過剰診断例)が出現してくる可能性もあるため、2つの検査の精度を比較する場合、滞在時間を考慮に入れる必要がある。地域相関研究(ecological study)
異なる地域集団の間で、ある要因の頻度(例:検診の受診率)とある健康現象の頻度(例:当該がんの死亡率)との関連を分析することにより、その因果関係を分析評価する研究手法。例えば、あるがん検診の受診率の高い地域ほど当該がんの死亡率が低ければ、その検診の死亡率減少効果を示唆するものといえる。この結果は理解しやすいものであるが、集団間の交絡因子(性・年齢・喫煙状況)の調整が困難であるため、結果の解釈は慎重に行われなければならない。致命率(fatality rate)
ある病気を持つ患者集団におけるある期間の死亡者の割合。死亡者数をその患者集団の人数で割ることによって計算する。生存率と対をなし、生存率は、(1-致命率)の関係にある。健常者を含めた対象集団全体で計算する死亡率と区別する必要がある。中間期がん(interval cancer)
一定の間隔でがん検診を実施しているとき、前の検診では陰性と判定されたのにもかかわらず、次の検診が来る前に自覚症状が出現してがんを発見される例のこと。偽陰性例の1つで、一般的には進行速度が速く予後不良である。トレード・オフ(trade off relationship)
検査精度の指標は、その検査における正常・異常の基準値によって変わる。検査値が高いほど異常である検査の場合、その基準値を低めに設定すれば、病気のある者のうち陽性と判定される割合は増えるので、感度は上がる。一方、病気がなくても陽性と判定される者(偽陽性)も増えるので、特異度は下がる。逆に、基準値を高めに設定すれば、特異度は上がるが、感度は下がる。このように、一方が上がれば他方が下がるような関係をトレード・オフの関係という。な行
任意型検診(opportunistic screening)
個人の死亡リスクの減少を目的とし、医療機関や検診機関が任意に提供する医療サービス。対象となる特定の集団は定義されないが、無症状であることが基本条件となる。具体的には、検診センターや医療機関などで行われている総合健診や人間ドックなどに含まれているがん検診が該当する。死亡率減少効果の証明された方法により検診が行われることが望ましいが、個人あるいは検診実施機関により、死亡率減少効果の不明な方法が選択される場合がある。がん検診の提供者は、対策型検診では推奨されていない方法を用いる場合には、死亡率減少効果が証明されていないこと、及び、当該検診による不利益について十分説明する責任を有する。は行
バイアス、偏り(bias)
調査や測定、分析や解釈の過程で、系統的に真の値から離れた結果を生じる誤りのこと。研究の計画実施にあたっては、バイアスの混入しない研究を計画することが重要であり、また研究結果を解釈する際には、バイアスの混入により結果にゆがみが生じていないかの吟味が必要となる。調査や測定、分析や解釈の過程で、系統的に真の値から離れた結果を生じる誤りのこと。研究の計画実施にあたっては、バイアスの混入しない研究を計画することが重要であり、また研究結果を解釈する際には、バイアスの混入により結果にゆがみが生じていないかの吟味が必要となる。
p値(p-value)
帰無仮説(通常は差がないという仮説)が正しい時に、偶然によって観察されたデータ上に差が生じる確率であり、観察された差の統計学的信頼性を示す。一般にこの値が5%未満(p<0.05と記載される)の場合、データに「統計学的有意差がある」とし、5%以上(Not significant: NSと記載される)の場合は「統計学的有意差がない」とする。費用効果分析(cost effectiveness analysis)
ある保健・医療サービスの実施に要する費用とそれにより得られる効果(自然単位による健康結果、生存年数の延長など)と比較検討する研究手法。1年生存延長に要する費用(費用効果比)を算出して、同じ効果をもたらす他の保健・医療サービスと比較する。費用効用分析(cost utility analysis)
費用効果分析の1手法であり、効果を効用値の重み付けで調整した単位を用いて、測定する。一般には、生活の質で調整した生存年(QALY)を測定し、費用/効用比を指標とする。費用便益分析(cost benefit analysis)
健康結果を貨幣価値により示したものが便益である。医療サービスに投入された費用と便益を比較検討する方法。例えば、早期発見・治療によって救命できた人が生産活動に復帰することによる経済価値を算出する。ま行
前向き研究(prospective study)・後ろ向き研究(retrospective study)
研究を立案、開始してから新たに生じる事象について調査する研究を前向き研究、過去の事象について調査する研究を後ろ向き研究と呼ぶ。無作為化比較対照試験は前向き研究の代表的なものであり、症例対照研究は、後ろ向き研究の代表的なものである。検診の有効性評価の場合、前向き研究では、研究開始後に行われた検診を評価し、後ろ向き研究はすでに行われた検診を評価することになる。前向き研究では、交絡因子を事前に把握することで、偏りの制御が可能となるが、研究結果が得られるまでにかなりの時間を要する。後ろ向き研究では、交絡因子の振り返っての把握が困難なため、偏りの制御が困難であるが、研究は比較的短時間に終了することが可能である。過去の診療記録を閲覧して、ある疾患の患者の予後やその予測因子を検討する研究は、遡及的に既存資料を利用する意味では後ろ向き研究であるが、因果推論の方向は「原因→結果」であり、疫学的には「後ろ向きコホート研究」とされる。マッチング(matching)
複数の集団で予後や要因曝露などを比較する際に、性・年齢などの関連因子を両群間で同一になるように対応させること。例えば、症例対照研究では、各症例に対して、性・年齢などが一致する対照例を選定する。検診発見がんと外来発見がんとで生存率を比較する際には、上記の要因が一致するペアを構成するように症例を収集するなど。これにより関連因子の影響を除外したうえで、検診の効果などをより正確に評価することが可能になる。無作為化比較対照試験(randomized controlled trial: RCT)
予防・治療の効果を科学的に評価するための介入研究。対象者を無作為に介入群(検診など、決められた方法での予防・治療を実施)と対照群(従来通りまたは何もしない)とに割り付け、その後の健康現象(罹患率・死亡率)を両群間で比較するもの。ランダム割付比較試験とも呼ばれる。日本語の用語は統一されていないので、Randomized Controlled Trialという英語を略したRCTという用語が使われることが多い。
メタ・アナリシス(meta-analysis)
1つの研究テーマに対して、複数の研究が行われた場合、結果にバラツキが生じることがある。これらを統合して解析する統計手法である。採用するデータは、系統的統括と同様な一定のルールに基づいて信頼できるものに絞り、それぞれに重み付けをして解析する。信頼性は高いものの、出版バイアス(publication bias:有意差がある結果のみが発表され、差がないという結果の研究が採用されにくい偏り)などの偏りにも留意が必要である。
や行
要精検率(recall rate)
スクリーニング検査の結果、精密検査が必要とされたものの割合。基本的にはスクリーニングテストの陽性率(positive rate)と同じである。ただし、画像診断や内視鏡検査ではがん以外の疾患が疑われ、精密検査や治療を要すると判断される場合があり、要精検率を他の施設や、他の検診と比較する場合、がんを疑ったものだけなのか、非がんを含んだものか基準が異なる場合がある。理想的には要精検率が低く、発見率が高いスクリーニング法が検診としては望ましい。ら行
ラテントがん(latent cancer)
死亡者の剖検により、はじめて発見される、死因とはならないがん。進展速度が比較的緩やかながんが該当し、その代表例が前立腺がんである。
ラベリング効果(labeling effect)
検診の結果を知ることによって受診者が受ける様々な心理的影響。例えば、スクリーニング検査の結果で要精密検査と言われただけで、「自分はがんではないか」と心配し、大変なストレスを受ける者もいる。これを「陰性のラベリング効果」と言う。逆に、検診で正常であったことを知ることにより、大いなる安心を得る者もいる。これにより、仕事や日常生活に対する活力が増すという「陽性のラベリング効果」もある。
リードタイム・バイアス(lead time bias)
検診発見がんと外来発見がんとの間で生存率を比較する際に問題となる偏り。がんの発生から死亡までの時間が検診発見群と外来発見群の両群で等しい(すなわち検診の効果がない)場合でも、検診で早期診断された時間の分(リードタイム)だけ、検診発見がん患者の生存時間は見かけ上長いことになり、したがって見かけ上の生存率もあがることになるという偏りである。生存期間の始点が早期発見の分だけずれるという意味から、ゼロタイム・シフトとも呼ばれる。利益・不利益(benefit・harm)
がん検診の利益としては、集団に対する死亡率減少効果が第 1であるが、このほか放置して進行がんで発見された場合に比べて、治療法や医療費が軽減される場合も利益の範疇に入る。一方、不利益としては、見逃し(偽陰性)や、偽陽性となった人に必要でない精密検査が行われることや、精神的不安を与えること、放射線被曝を被ること、無駄な医療費が必要となることなどである。またたとえがんであっても、精密検査や治療の結果重篤な偶発症を被ることや過剰診断(overdiagnosis)も不利益の範疇に入る。罹患率(incidence rate)
ある集団においてがんに新しく罹患した者の数をその対象集団の観察人年(対象者個人の追跡期間の総和)で割って得られる。通常は、人口千人年対あるいは人口10万人年対等(すなわち人口千人あるいは10万人を1年間追跡した場合に新たに罹患する割合)で表す。有病率との(ある時点における、ある集団においてある病気を有する者の割合)違いに注意する。
レングス・バイアス(length bias)
がんの成長速度の差によるバイアスである。検診では成長速度の遅いがんのグループが発見される可能性が高くなる(レングス・バイアスド・サンプリングとも呼ばれる)。成長速度の遅いがんは、成長速度の速いがんに比べて一般に予後が良好である。したがって、検診発見がんと外来発見がんとで予後や生存率が異なっていたとしても、それが検診の効果なのか、あるいは各々で発見されるがんの成長速度の違いに由来するものなのか判別し難いというバイアスである。